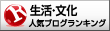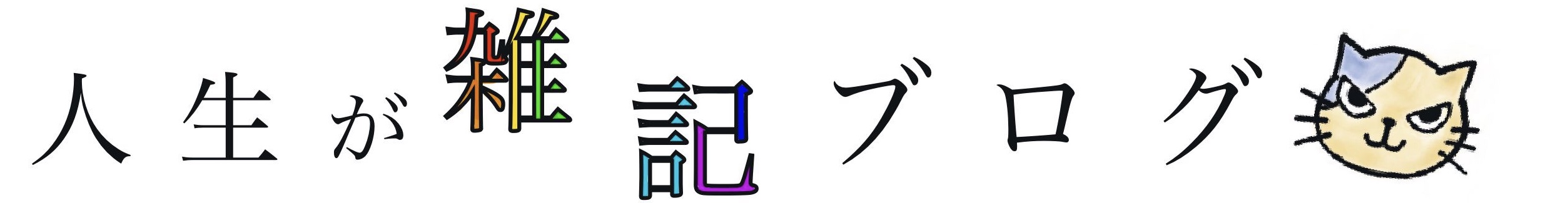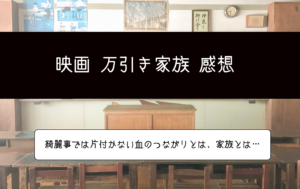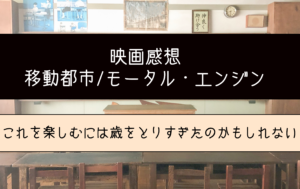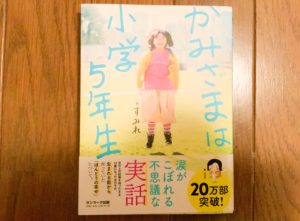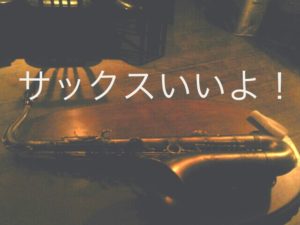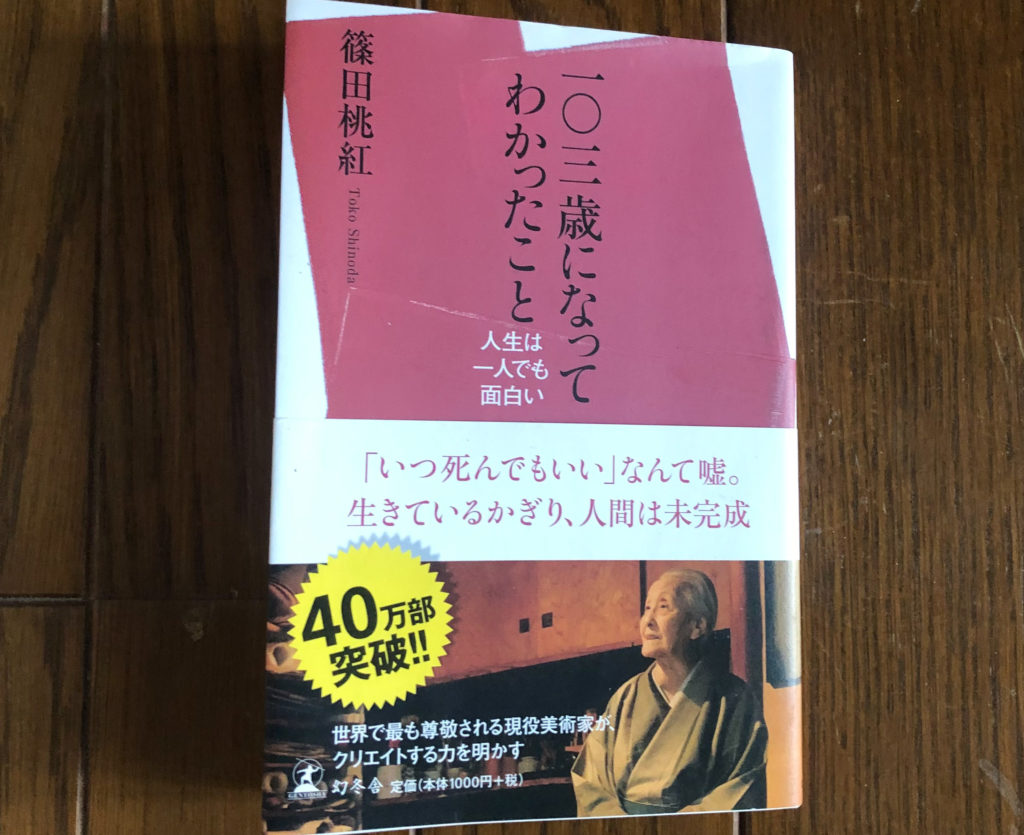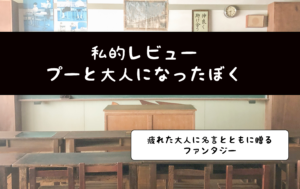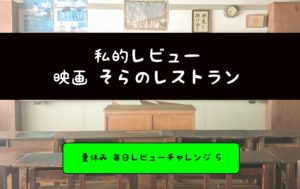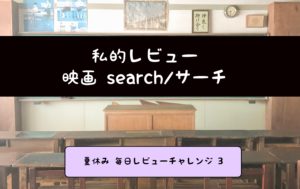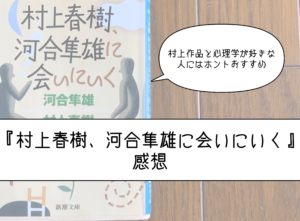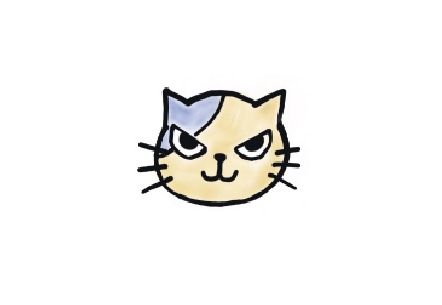毎日何かしらのレビューを書く!と、自らに課して始まった8月。子供と1日遊ぼうと、寝不足になろうと、何とか書いてきたけれど、ついに穴を開けてしまいました(笑)いや、ちょっと体調が悪くてですね。偏頭痛もちでしてね←言い訳
自分で決めただけのこと、誰に迷惑をかけるわけでもないのに、〆切を守れない、という状態は少なからず胃に重たいものを感じさせます。
あぁ〜、自分で決めたことも守れないのか…私って… 昔からそうなんだよね。いろんなことがちぃっとも守れない。なんて
そんな中だったからでしょうか、図書館に行った時にこの本が、運命のように目に入ってきました。
その名も〆切本。名だたる文豪や作家たちが、〆切に関して書き記したエッセイや書簡などを集めたものです。
余談ですけど、〆切って英語でdeadlineと言うのですね(笑)命かかってますね(笑)
もくじ
感想21 〆切本 感想
文豪たちの言い訳、開き直りが、何だかホッとしたり笑えたり
もうね、表紙からしてクスッと笑えるんですよ。「どうしても書けぬ」「あやまりに文芸春秋社へ行く」「ほんとに風邪引いたんですか」「ほんとだよ」
いいでしょ。いいんです。あんな傑作、名作、名文を世に生み出してきた作家さん達も、書けなくて死にそうな思いをしたんだなぁ、とか、自分と並べて語るのはおこがましいんですけど、ちょっと勇気をもらいます。
この本の最初のエッセイが、田山花袋さんの“机”というエッセイなんですけど、この中の言葉
「今夜、やる。今夜こそやる。……」
原稿用紙を並べて、書き出そうとしても、どうも気に入らなくて書けない、妻は「まだ駄目ですか。」と聞く。編集のT君に「だって、出来ないんだから。」と開き直る。終には、筆と紙とを見るのが苦しくなる。
と、こんな調子なんです。最初からものすごく共感というか、わかる。これわかる!っとなりました。何も文章を書くことに限定したことではなく、この本は何でもやらなければいけないことが迫っている時に当てはめて考えることができます。
例えば、部屋の片付けとかさ(笑)資格試験の勉強とかさ。
「今夜、やる。今夜こそやる。」っていってるもんね。少なくとも心の中でさ。
結局田山花袋さんは、夜中にふと興が湧いてきて、一気に書き上げていくのですが、
ところが、ふと、夜中などに興が湧いてきて、ひとりで起きて、そして筆を執る。筆が手と心と共に走る。その嬉しさ!力強さ!またその楽しさ!
と表現しております。そうなんですよね。一度やる気が出た時って、心身ともに乗ってくる感覚がありますもんね。まぁ、小説を書いたりするのは、また特別大変だと思うのだけど…
大岡昇平さんの“文士の息子”という話も笑えます。
大岡昇平の息子さんが中学2年か3年の頃、作家の家庭を取材に来たラジオのアナウンサーが息子さんに聞きます。
「大きくなったら、やはり、お父さんみたいな仕事をやりたいですか」と聞いた時、断乎として「いやです」と答えた時には、少しドキッとした。
「なぜ、いやですか」
「ねむいから、いやです」
この返事は、伸び盛りの子供らしい無邪気な返事と考えられた。
「なるほど、お父さんみたいに徹夜で原稿を書くのはいやなんですね」とアナウンサーが追求した。
「それだけじゃありません。始終うそをついてあやまってばかりいなければいけないからいやです」
ちょっと笑えますよね。いつも原稿が締切りぎりぎりでないと出来上がらない癖があり、「すみませんが、もう1日待ってくれませんか」と電話口で平身低頭ばかりしているのを見ているのだと。1枚もできていないのに「10枚までいったとこなんですが」とか「不意に客がありましてね」とか、風邪を引いたとか腹が悪くなったとか、苦しい口実を発明する現場を見られていた、と、その後解説されています。
その他にも菊池寛さんは新聞連載の地獄を綴り、梶山季之さんは正月前の〆切繰り上げの忙しさを“なぜ正月なんかがあるんだろう”というエッセイに綴っています。
夏目漱石さんの書簡から、藤子不二雄さんや長谷川町子さんのエピソードが漫画で掲載されていたり、読んでいて飽きなかったです。私は昔、新井素子さんのファンだったのですが、新井素子さんのエッセイが載っていたのも嬉しかったです。
その他、泉鏡花、志賀直哉、谷崎潤一郎、吉川英治、横光利一、林芙美子、幸田文、坂口安吾、太宰治、松本清張、井上ひさし等々…(敬称略)全部で90人のエッセイや手紙が掲載されています。
豪華ですよね〜
編集者も大変よね
この本は、編集者の立場に立ったエッセイもたくさん載っていて、〆切を守らない作家に困りながらも愛を持って見守っている編集者のこともよく理解ができます。
私は村上春樹さんのエッセイの大ファンなのですが、“植字工悲話”という村上春樹さんのエッセイも載っています。文字通り、編集の苦労を通り越して、印刷所に勤めるお父さんにまで発想を飛ばしております(笑)
人生は〆切
中には〆切は大事。絶対に守る。守るべきもの、みたいなことを書かれているものもありますけど、それは真っ当な考え方!もちろんそうできれば一番だよね。
そうなんですよ。人生って、〆切がないといつまでもだらだらしちゃうし、大きな仕事ってやり遂げられない。でも、伸ばせる〆切は伸ばしたっていいじゃん。あやまったり、可能な範囲で〆切を伸ばしたり、泣いたりわめいたり、平身低頭謝って、「仕方がないなぁ」なんて言われながら、なんとか出来上がった原稿を渡して、ほっとくつろぐ、コーヒーがうまい!みたいな。
〆切があって煮詰まるから、ポンと抜けて傑作ができることもあるだろうし。結局できなくて、穴を開けることもまた人生。人を傷つけたり、殺したりする以外は、堂々と謝ってしまうことも方法かもしれません。
この本の最後に掲載されているのが、柴田錬三郎さんの“作者おことわり”という文章ですが、これがまた面白い。煮詰まって何一つ言葉が出てこなくなった柴田さん、読者に対して、なぜ書けなかったか、を滔々と綴った文章を編集者に渡そうと書き上げます。
〆切ギリギリで渡した文章は、すぐに印刷所へ走るので、編集者はその場では確認しない、ということを知った上での確信犯です。
そして、そのような原稿を仕上げた後、ゆったりとブルーマウンテンを飲みながら、さも原稿が仕上がったかのように振舞おう。印刷所で読んでみて愕然となるかもしれない、この文章に横尾忠則氏はどのようなイラストを描くのだろう、なんて考えているのです(笑)
クスッと笑えて、なんだか元気が出ました。
まとめます
エッセイも手紙も、どの文章もきれいなんですよね。やっぱり文豪や作家さんたちは、文章がきれい(当たり前か(笑))〆切の愚痴さえも文学ですね。そこはちょっと羨ましい(≧∀≦)
〆切や〆切が守れない、ということに対して、これだけの感情のひだや、考えをまとめることができる、ということがプロの作家さんたちの凄さだなぁと思いました。
それと同時に、このちょっと不完全な人間らしい部分があるからこそ、素晴らしい文学が書けるのだろうなぁとも。完璧な人(完璧に近い人)の書く文章は、ハウツー本にはなっても文学にはならないのかもしれません。
この本の中に、小川洋子さんがかいた“イーヨーのつぼの中”というエッセイがあって、〆切が近いのに言葉が浮かばずに苦しみながら、こんなことを書いています
白い沼に落ちてゆく最中には、「がんばれ。君なら書ける。さあ勇気を出して前進するのだ」と威勢良く大声を発する人より、イーヨーのようにため息をつきながら、底の底まで一緒に沈んでくれる人の方が必要になってくる。エネルギーにあふれた自信満々の人は、結局沼のほとりの安全な場所に立って、こちらをのぞき込んでいるにすぎない。その人の励ましはどこにもたどり着けないまま、空しく泡となって弾けていく。ああ、あの人はどんどん素晴らしい原稿が書ける才能を持っているんだなあ、それに比べて自分は……と、ますます憂鬱になるばかりだ。
それに引き換えイーヨーはなんと心優しいのだろう。助けを求める人の手を無理に引っ張っても、ただ痛い思いをさせるだけだし、自分にできるのはせいぜい一緒にため息をつくくらいのことだ、と心得ている。
この本は、イーヨーのような本。なんだかうまくいかない時に、一緒に沼に沈んで、そこから何か浮上するきっかけになるような、そんな本でした。
うまくいっている時でも単純に、きれいな文章を読むのが楽しい本だと思います(≧∀≦)
2も出ているのですね(≧∀≦) これ読みたい!